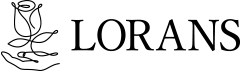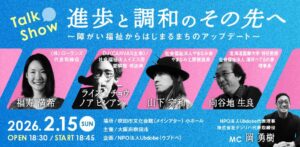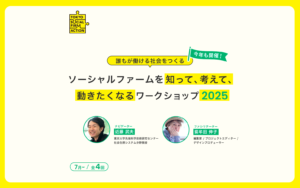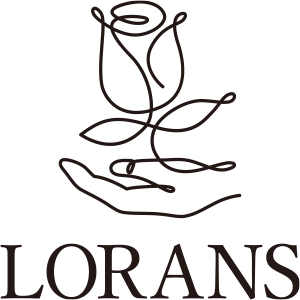2025年6月、ローランズは福祉先進国・スウェーデンを訪問し、障害者の就労支援制度や雇用現場を視察しました。
本レポートでは、スウェーデン政府が出資する国営の障害者就労支援企業であるサムハル(Samhall)などの視察内容を通じて得た気づきと、日本の障害者雇用における示唆、そしてローランズが今後目指すべき方向性をお伝えします。
視察概要
●日程:2025年6月9日〜6月11日
●参加者:
株式会社ローランズ 1名
一般社団法人ローランズプラス 1名
ウィズダイバーシティ有限事業組合 1名
事業推進関係者 2名
●主な訪問先
視察の背景
ローランズには、スタッフ約120人中、障害や難病と向き合うスタッフが約90名います。
ローランズは創業以来、「みんなみんなみんな咲け」をミッションステートメントに掲げ、花や緑の空間装飾、カフェ、オフィス業務、花を育てる「ローランズファーム横須賀」など、多様な業務を通じて、障害のある人たちがそれぞれの持ち味を発揮しながら働く場を共につくってきました。
今回のスウェーデン視察は、スウェーデンの障害者就労支援や福祉的な働き方の先進事例を学び、日本におけるローランズの障害者雇用戦略の発展に資する知見を得て、ローランズ事業戦略のアップデートに活用することを目的として企画されました。
視察の様子(一部抜粋)
就労支援機関「Jobbtorg Stockholm」(ストックホルム市)
スウェーデン到着後、ローランズ一行が最初に向かったのは、スウェーデンの首都・ストックホルム市が運営する就労支援機関「Jobbtorg Stockholm」。ここでは、スウェーデンの障害雇用の仕組みについて学びを深めました。

支援の担い手は行政(国や市町村)
スウェーデンでは、障害のある人がまず訪れるのは「公共職業安定所」(日本のハローワークに相当)です。ここでは、就労における知識やスキルについて、国が設計したシステムに基づき、就労可能性について判断が行われます。
一般企業での就労が難しいとされる人は、スウェーデン政府が出資する国営の障害者就労支援企業・サムハル(Samhall)に案内されます。サムハルの業務に従事するために必要な知識やスキルの習得がまだ十分でないと判断された場合には、市町村がサポートを担います。
日本との主な違いは下表のとおりです。
| 日本 | スウェーデン | |
| 支援の入口 | ハローワークや民間の就労移行支援など | 公共職業安定所に集約 |
| 支援の担い手 | 就労継続支援(A型・B型)などの民間事業所が主体 | 国や市が主体(公営) |
| 支援制度設計の思想 | 法定雇用率制度に基づき、民間企業の雇用数を増やす=雇用がゴール | 障害者の「社会参加」や「自立支援」がゴール |
給与について
働く障害のある方へ支払われる給与についても違いがありました。日本では障害者雇用を行うと行政の助成金が出る場合がありますが、原則、雇用している事業主が障害者へ給与を支払います。
スウェーデンの場合、就職が決まると、最初の2年間は国と市が給与の50%ずつを補助します。つまり、企業は障害者スタッフの給与を負担しません。2年後には企業と国で50%ずつ負担します。
チームでスーパー業務に従事:ICA(イーカ) Maxi Gnista(ウブサラ市)


次に向かったのは、ウブサラ市にあるスーパーマーケット「ICA(イーカ) Maxi Gnista」。
このスーパーマーケットでは、店舗内に『リソースチーム(Resource Team)』と呼ばれる障害者支援チームが配置されており、ウブサラ市のデイアクティビティセンター(※)の一部として運営されています。
※障害のために就労や就学が難しい人々が、日中の活動を通して社会参加や自立を支援される場所
このリソースチームは、7人の障害者で構成され、1日に最大6名が勤務していました。市のスタッフが1名現場支援を担い、チームに任された業務に一緒に取り組みながら、障害者スタッフの仕事内容やサポート体制を調整しています。
リソースチームが担当する業務は、パンや牛乳の陳列など限定された売場に絞られており、冷凍食品や賞味期限の短い商品は扱いません。他の従業員と同じ制服を着用し、「Resource Team」のバッジを付けて勤務しています。
リソースチームの障害者は、労働に対する給料を受け取っていません。しかし、福祉制度として行政から支援を受けており、生活は社会保障で成り立つ仕組みになっています。リソースチームの存在により、職場の雰囲気が明るくなり、他のスタッフや顧客にも良い影響を与えているという副次的効果もあるとのことです。
ウプサラ市では約800人がこのようなデイアクティビティに参加しており、市職員による支援が組織的に行われています。
スウェーデンの障害者雇用では、働いて「給与を得ること」よりも「社会参加すること」が重視され、企業と福祉制度が連携してその場を確保されている点に、ローランズスタッフも大きな学びを得ました。
リソースチームのスタッフの声
- Hさん:週5日勤務。パンや牛乳の陳列、カフェ業務などを担当。「音がうるさい場所」や「濡れる作業」は合わなかったが、ここの仕事は自分に合っていると実感した。
- Aさん:勤務3年目。週3日勤務からスタートし、現在は週4日勤務に。スパイスやシリアルの陳列を担当。
- Pさん:2016年から勤務。接客が好きで、長期的にここで働きたいと希望している。将来も他の業務は望まず、今の仕事を継続したいという意向を持っている。
国営の就労支援企業「Samhall facility at Lunda」(サムハル)




サムハル(Samhall)とは
翌日6/10は、スウェーデン政府が出資する国営の障害者就労支援企業であるサムハル(Samhall)を訪問。サムハルは全国に800以上の拠点と12,000カ所の職場を持ち、24の職種を提供しています。
今回、ローランズ一行が訪問したルンダ工場には約100人が勤務しており、福祉的な就労と職業訓練の両面から障害者の社会参加を支えていました。
サムハルが提供する24種の職種には、製造、清掃、ランドリー、ケアサービス、配送、施設管理などがあり、利用者の多様な適性に対応できます。今回訪問したルンダ施設では、ベアリングの箱詰めや組立、自動車関連部品の検品などが行われていました。
就業前にはアセスメント(適性評価)を行い、本人に適した職種を見つけるまで何度でも配置を繰り返すそうです。就業後もエリアマネージャー(1人で約30人を担当)が伴走支援を行い、業務定着に向けたサポートを行っています。
1500人の一般就労への移行を目指す
サムハルでは年間1,500人の一般就労(Regular Labor Market)移行を目標にしており、訪問したルンダ工場でも年間14人の移行を掲げていました(訪問時点では6名達成)。一般就労後12カ月以内であれば、サムハルに戻ることも可能です。
ただし、多くの利用者はサムハルの安心できる環境に満足しているという側面もあり、あえて一般就労を望まない傾向も見られるとの話もありました。
ローランズスタッフが、今回初めてサムハルを訪問して感じたことは、サムハルは日本でいう「巨大な就労継続支援A型事業所」ではないか、という点です。福祉的な就労と訓練の中間的な存在であり、幅広い職種があるため、障害者にマッチする業務を見つけやすい点に学びがありました。
就労継続支援事業所を運営するローランズとしても、一般就労をゴールとする支援制度設計が必要であると思う一方で、「本人の希望」に合わせA型事業所で働き続けたいという障害者に対しては無理な就職支援とならないように注意すべきであるという意見も出ました。
また、サムハルでも多くの障害者が清掃の業務に従事することが多いことを聞き、障害者の職種の選択肢が狭いことは世界共通の課題であることを認識すると共に、ローランズが展開する「花」の職種提供がいかに価値が高いであるかを実感するものでした。
障害者の働く選択肢において、もっと職種領域を広げる方法はないか、と帰国後メンバーで議論しているところです。
自閉症の方のみ雇うITコンサル企業:Unicus Sverige AB


最終日6/11に訪問した「Unicus Sverige AB」は、ITコンサルティングを提供する民間企業です。自閉症の方だけを雇用し、自閉症の特性(集中力、ルーティン業務の継続力など)を強みにしたデータ分析や品質管理などで成果を上げており、顧客には銀行や保険会社などがあります。
この企業は、事業を北欧各国で展開し、スウェーデンには約60名のコンサルタントが在籍しています。採用基準は「プログラミング言語が1つ以上できる」「学び続ける意欲がある」などです。
他の企業への研修プログラムの提供も行っており、企業内での自閉症理解向上にも寄与しています。「特定障害に特化したプロフェッショナル集団」というモデルは、日本の障害者雇用でも選択肢となり得るのではと、ローランズスタッフも大きな示唆を得た現場になりました。
職種起点で特性に応じた配置をする発想は、まだ日本では少ないものです。しかし、特性=スタッフの得意を前提にした職場設計は、結果として他の社員にとっても働きやすい環境を生んでいるのではないでしょうか。
ローランズスタッフが視察で得たこと
社会との接点を持ち、日々の居場所をつくること
スウェーデンは、1960年代のノーマライゼーションの流れをきっかけに、障害者が一般市民と同様の普通(ノーマル)の生活・権利などが保障されるような環境整備を行ってきました。したがって、スウェーデンの障害者雇用の土台として、障害者が社会との接点を持ち、日々の居場所を得ることの価値が強く意識されています。
例えば、裁判所内のカフェ、スーパー、園芸店など日常のあらゆる場に障害者が自然に溶け込んでおり、「自然と見守る風土が醸成されている」ことが根付いていると感じられました。
対して、日本では一般企業での就労も進みつつありますが、障害当事者が就労支援施設やサテライトオフィス等、健常者が働く場と切り離された場で働き、相互の交流が乏しいという一面があります。
スウェーデンでは障害者雇用を国や市町村が行っているという、民間主導の日本とは異なる制度であることもありますが、就労支援と生活支援がスムーズに接続されており、働く場が単なる“雇用の場”ではなく、地域や生活に根ざした“居場所”となっていました。
私たち日本障害者雇用の場でも、「雇う」ことがゴールではなく、これから「雇用の質」を高めるうえでは、スウェーデンが1960年代以降築いてきた、共生社会のあり方について学ぶ部分は多いのではないかと考えます。
一方、現地で印象的だったのは、「必要な人材を雇用する」「事業の戦力になれる人を雇う」という、合理的(システマチック)な支援設計です。
日本のように法定雇用率によって企業が努力義務を負う構造とは異なり、スウェーデンの障害者雇用は、本人の働く意欲ではなく、国が定めたスキルアセスメントや支援制度にあてはめた運用がされていた点は、視察チームが訪問前にイメージしていたものとギャップがあったことがとても印象的でした。
ただ職種を増やすのではなく、“特性に合った職種”を創る
視察を通じて得た最大の気づきは、「職種を増やす」こと以上に、「その人の特性が活かされる職種を新しく創る」という視点です。
サムハルでは24にわたる職種があるからこそ、数万人という障害者雇用を生み出していました。また、自閉症の方のみ雇うITコンサル企業(Unicus Sverige AB)では、自閉症の方が「できる」「得意」という特性を活かした業務内容の提供に特化していました。
障害者が働ける業務を“企業が提供して選んでもらう”のではなく、当事者の特性や強みを生かした仕事を“共に創る”姿勢こそ、これからの時代に求められる雇用のあり方ではないでしょうか。
ローランズや障害者共同雇用の仕組みでは今後、これまで提供してきた職種にとどまらず、特性にあった職種を創り出すことが必要ではないか、と話しています。
ローランズ代表:福寿からのメッセージ
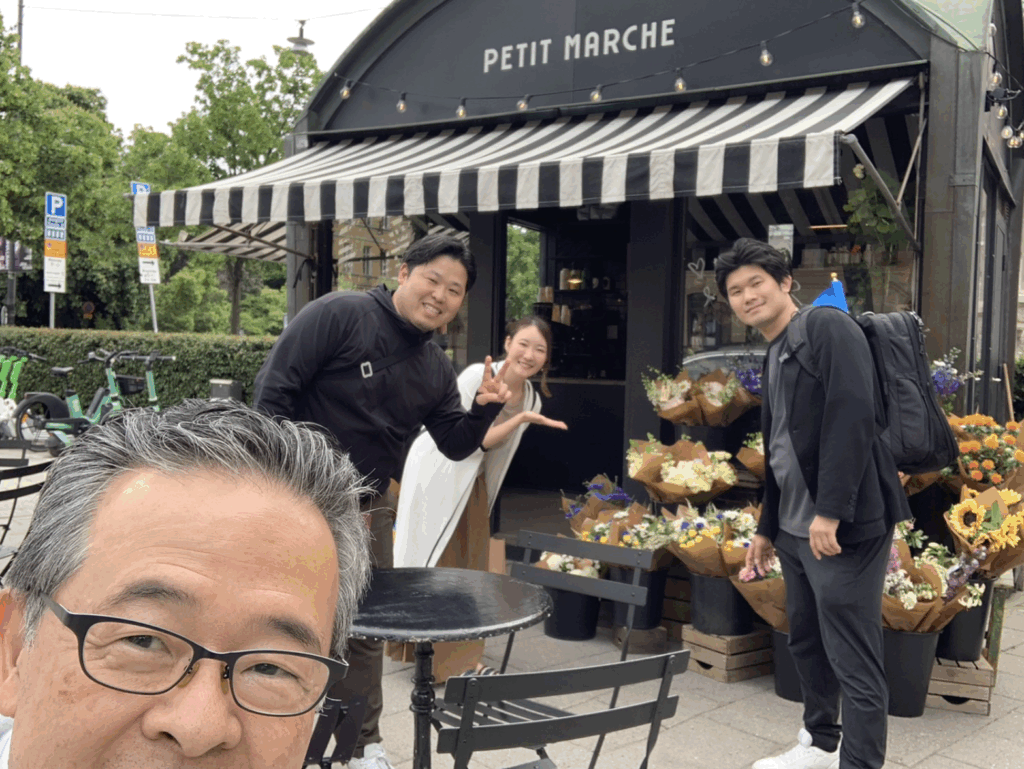
日本では2026年7月に法定雇用率が2.7%に引き上げられることが決定していますが、厚生労働省の最新調査では法定雇用率を達成している企業は46.0%にとどまっています。これは、日本の多くの企業、中でも特に中小企業が制度目標に追いつけずにいる現実を意味しています。
経営リソースが大企業に比べ限られている中小企業が、いかに障害者雇用を諦めずに取り組んでいけるような仕組みの設計作りと、障害者雇用の受け皿を広げる努力が引き続き求められる一方、「どのような職場で」「どのような支援体制のもとで」「本人が納得感をもって働けるか」といった「雇用の質」の議論がますます重要になっています。
スウェーデンと日本では、障害者就労支援の制度設計や担い手に大きな違いがありますが、「本人が自分の特性を活かせる環境で安心して働けること」「社会との接点と居場所をつくること」が共通のゴールであることがわかりました。
これから、私たちローランズは、「花屋」という枠にとらわれず、「なりたい自分になるための仕事」を提供できる場を作っていきたいと考えています。そのためにも、より多くの職種、多様な働き方を創り出し、「みんなみんなみんな咲け」の社会の実現に向けて、これからも挑戦を続けていきます。
株式会社ローランズ 代表取締役 福寿 満希